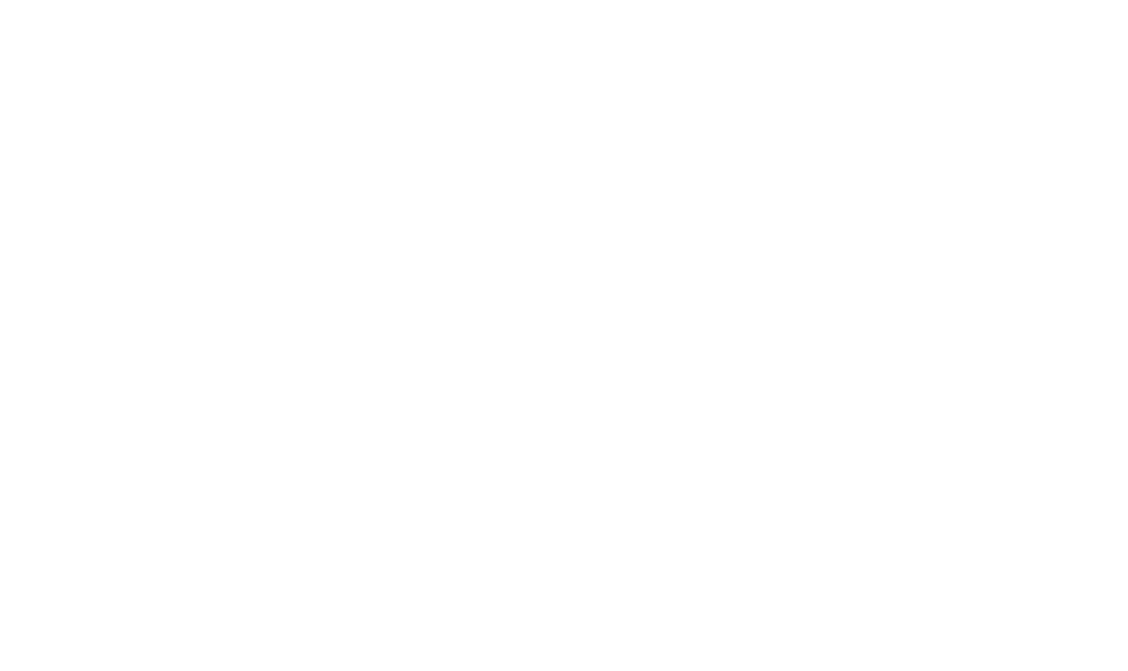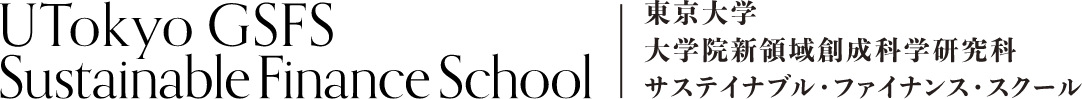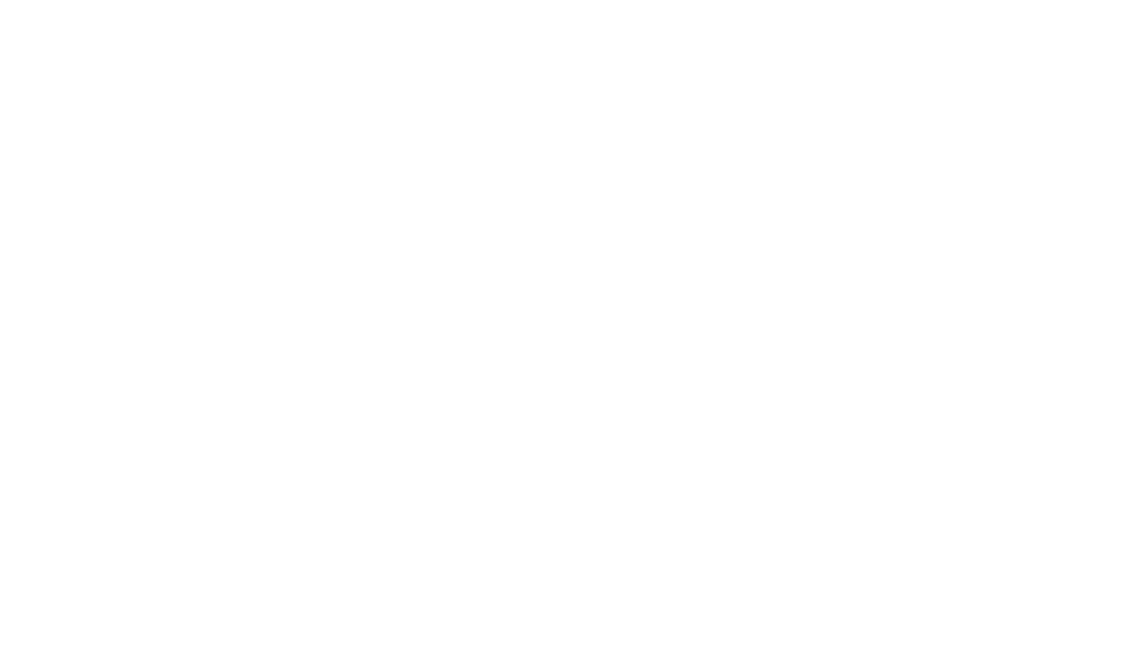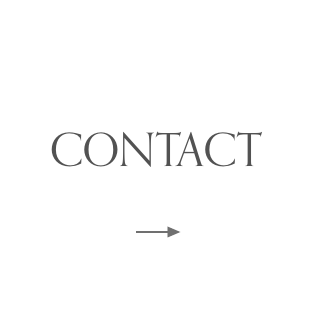コース
COURSE
当スクールでは下記のコースをご用意しています。
・夏季コース & 冬季コース(対面中心 中級~上級)
・オンデマンドフル & ライトコース(常時受講可 初級)
ご挨拶
GREETING

藤井 輝夫
新型コロナウイルス感染症や気候変動など、私たち人類社会はいま地球規模の課題に直面しており、それに伴って世界各所で社会の分断や格差が露わになってきています。近年では、これらの社会課題が企業のリスクとしても認識され、そうしたリスクに対して十分に準備・配慮できているかという観点から企業が評価されるようになりつつあります。
このような社会変化に対応すべく、東京大学では、大学院新領域創成科学研究科による新しい社会人教育プログラム「サステイナブル・ファイナンス・スクール」を2023年度に立ち上げました。サステイナブル・ファイナンスの概念は、金融界に限らず全ての企業が事業活動を行う際に配慮すべき指針であり、それを担う人材の育成は急務です。
このスクールで学んだ社会人の皆様が、今後の日本経済を担う、地域再生に取り組む、ひいては国際社会をリードするなど、それぞれの立場で活躍していただくことを願っています。私たちもまた、このスクールを通じて受講生の皆様と社会課題を共有し、共にその解決に取り組んでいけるよう、双方向の対話が深まることを期待しています。
本スクールについて
ABOUT

サステイナブル・ファイナンス
推進に寄与する人材を育てます。
本スクールは、人類社会のサステイナビリティを確保するためのファイナンスのあり方、すなわち「サステイナブル・ファイナンス」について、その背景と目的、理論的基礎、世界の潮流、実務知識等を広く学ぶとともに、そのあるべき将来に関して、参加者自らが問題意識をもって考察する機会を提供します。東京大学や国立環境研究所などアカデミアと実務界から、国内外のサステイナビリティ分野の第一線で活躍する講師陣を招いて、講義を行い、参加者と議論を深めます。
金融界・産業界での実務経験のある中堅人材を主な対象に、自らの業務のみならず企業・金融機関や業界の進むべき方向を、サステイナビリティの視点から見つめ直し高めるための主体的・総合的な「考える力」と「行動する力」を育成することを目標とします。また、本スクールでは、年度を越えて参加者や講師間のネットワーキングをサポートし、日本のサステイナブル・ファイナンスをリードする人々が切磋し合い連携する機会を提供します。
なお、2024年度より、東京大学エクステンション株式会社(東京大学100%出資会社)が業務の一部を担うことになりました。
本スクールでは、サステイナビリティを志向する世界の潮流の中でリーダーシップを発揮できる理論的基盤や主体的な考察力・情報収集能力を身に付けることを目指し、4段階での能力構築を実施します。
- サステイナビリティ問題の中核である地球環境の状況を科学的に把握する。それにより、世界的なサステイナビリティの潮流の背景を正しく理解し、グローバルな視点で考えられるようになる。
- サステイナブル・ファイナンスに関連する理論的基礎を学ぶ。グローバル経済の負の外部性としての課題やその解消方法を理解し、経済・金融市場とサステイナビリティの関係を考える上の基礎を身に付ける。
- 様々な当事者による取り組みとその意義・実務動向の理解を深める。グリーン・ファイナンス、ESG投融資、企業情報開示等について、最新動向を知るとともに、そのメカニズムや効果について自らの考えを持てるようになる。
- サステイナビリティに関する政府や中央銀行の取り組みを学ぶ、各講義ではQ&Aと講師との議論を通じて理解をさらに深める。対面講義でグループワークを実施する。
MEMBER PAGE
MEMBER専用ページ
MEMBER専用ページはこちら